会社設立に年齢制限はあるのでしょうか?また、年齢以外に会社設立の制限項目はあるのでしょうか?会社には設立や運営等に関する法律があり、その法律を見ていくことで会社に関しての様々を知ることができます。そこで今回の記事では、株式の譲渡方法や未成年にも株式は譲渡できるのか、そして会社設立に年齢制限はあるのかについて詳しく解説します。会社設立時の注意事項や要点を知る一助として参考にしてみてください。
目次
1 株式、株主、株主譲渡とは

そもそも「株式」とは、株式会社が事業を行うために必要な資金を調達する際に、その資金と引き換えに発行する証券のことです。株式会社に出資をした人は、出資した金額分のその会社の株式を受け取り、「株主」となります。
株主には、保有している数(割合)に応じたその会社の経営権が与えられます。例えば、発行済株式数が100で、その100株を全て1人が保有しているとすると、その1人が100%会社の経営権を持っているということになります。
「株式譲渡」とは、株主が自身の保有する株式を、多くの場合は対価と引き換えに他者に譲渡することです。株式譲渡の多くは、中小企業の社長兼株主が会社を後継者に託す際や、中小企業のM&A(会社の合併(Mergers)・買収(Acquisitions))時に行われます。
中小企業のM&Aにおける株式譲渡は、株式を譲渡する側(売り手側)と譲渡される側(買い手側)が譲渡金額を決めて契約を結び、譲渡料を支払って株式交付する際に、すなわち契約遂行時に行われます。
このときの株式譲渡には3種類の方法があります。1つ目は上場企業の株式を対象に証券取引所等によって行う「市場買付」で、2つ目は公告によって市場外で不特定多数の株主から株式を買い集める「公開買付(TOB)」、そして3つ目は直接株主と株式のやり取りを行う「相対取引」です。
この3種類をそれぞれもう少し詳しく見ていきましょう。まず市場買付とは、上場企業の株式を、証券取引所を通して対価を支払うことにより、その企業の株式を取得する方法です。
もし、市場買付により発行済株式総数、また潜在株式総数の合計の5%超となる株式を取得した際には、その取得日から5営業日のうちに、管轄の財務局へ大量保有報告書を提出するというルールがあります。
また、取得した株式の保有割合の1%を超えた変動があった場合にも、変更報告書を提出することになります。すなわち(目立つ)市場買付は、株式譲渡の動きが周知されるところになるということです。買い集めが分かると株価が高騰する可能性があるため、会社の買収に市場買付という方法が選択されることは通常ありません。
2つ目の公開買付(TOB)とは、期間や価格などの買付条件の公告をすることで、不特定多数に向けて市場外(取引所外)で株式譲渡を進めるものです。
公開買付は、上場企業の株式を大量に購入する場合や、会社を買収・合併・子会社化する場合、また非上場化するために経営陣が買収する(MBO)場合に行われます。
通常、公開買付は買い集めやすくするために、買付価格を割高に設定します。また、公開買付の買付条件には株式に上限数が設けられていることがあったり、公開買付自体が不成立となったり中止になったりすることがあるため、もし公開買付を行う場合には、この点を注意する必要があります。
3つ目の相対取引は、現在の株主と直接交渉をして行う株式譲渡手段で、非上場企業の株式譲渡を行う場合に多く行われます。株主が複数の場合はそれぞれに交渉が発生するため、時間も手間もかかることになります。
また直接交渉であるため、買付価格が株主によって異なる場合があります。その場合、株主間で買付価格に不満が生じることが往々にしてあるため、通常は同一価格での買付を進めます。
株式譲渡のメリットとデメリットにも触れておきましょう。まずメリットについて見ていきます。会社間で50%超の株式譲渡が行われることにより、買い手側は親会社、売り手側は子会社という関係が成り立ちます。
売買する両者の思惑が一致した円満な株式譲渡である場合、双方の事業内容やブランドは相乗効果を持ち、事業の拡大に至る可能性が高まります。これが株式譲渡のメリットの1つです。
そして、もし経営者が高齢化により引退して会社も廃業をするとなると、従業員は職を失い、社会にとってもその会社が持つ技術やブランドを失うことになります。しかし、このとき経営者が株式譲渡という手段を選ぶことで、会社は存命し従業員も雇用が継続される目が出てくる、というメリットもあります。
デメリットには、株式譲渡は経営者の変更に繋がるため、体制や社風の変化が生じることにより、従業員が動揺したり、経営方針が変わることによりブランドにも影響が出て、ブランド力が弱まったりする場合があることが上げられます。
また、株式譲渡は会社の経営権の譲渡ということですが、譲渡するものには負債といった負の財産や、そして通常の帳簿では分からなかった簿外債務といったものも含まれます。
買付を検討している側がこの会社には負債が多いと判断した場合、または簿外債務が顕になった場合、買付から身を引く可能性があります。そうなると思うように株式譲渡が進まず、期待したような売却益を得られないということになります。
また、負債が多いと買い叩かれることもあります。不振の事業があれば企業価値は更に低くなり、結果、期待していたほどの売却益を得ることができず、その上経営権をも手放すという事態に陥ることも考えられます。
2 株式譲渡、事業譲渡、会社合併の違い

次に、株式譲渡とは似て非なるものである「事業譲渡」と「会社合併」の特徴、またメリットとデメリットを見ていきましょう。
株式譲渡のメリットには、手続きが容易であること、そして譲渡後も会社が存続してブランドや従業員の雇用が継続されることがあります。
一方、株式譲渡のデメリットには、株主が多数の場合交渉が進まない(進みにくい)こと、そして負債や簿外債務等のリスクを掴まされる場合があるというものがあります。
それでは事業譲渡について見ていきます。事業譲渡とは、現在の株式保有者(株主)を変動することなく会社の事業を売却する方法です。このとき売却する事業は、一部のみの場合と全ての場合があります。
事業譲渡は事業の再編を考えている場合、また会社の立て直しを図りたい場合に行います。好調な事業を敢えて売却することで資金を得る、または自社事業が魅力的に映る他社に売却することによって資金を得るのが事業譲渡です。
事業のみの譲渡なので、会社の経営陣、株主は従前通りの体制となります。従業員の雇用も継続されますが、売却する事業を担当している従業員については異動するか、場合によっては売却先に転籍することもあり得るでしょう。
買い手にとっては簿外債務等のリスクを回避でき、希望する事業のみを引き継げることがメリットですが、手続きが多く税負担も大きいのがデメリットです。
会社合併とは、合併会社が被合併会社を吸収するというものです。被合併会社の資産や負債、契約や権利、そして簿外債務といったものの全てが合併会社に引き継がれることになります。既存の会社への合併を吸収合併と呼び、新たに設立する会社への合併を新設合併と呼びます。
会社合併のメリットには、1つの会社を丸ごと吸収することから、合併した方の会社は事業規模をその分大きくできるというものがあります。一方、デメリットは、多くの手間と合併の過程で多くの費用が発生すること、簿外債務等のリスクがあること等が挙げられます。
3 未成年者の株式譲渡について

それでは未成年者に株式譲渡を行えるのかについて見ていきましょう。
3-1 未成年者へも株式譲渡は可能
実際、未成年者への株式譲渡は可能です。例えば、未成年者へ株式譲渡を行うケースとして、事業承継や家族経営をするため等が挙げられます。このように家族間で株式譲渡を行う場合、株式譲渡の方法以外にも、「相続」や「贈与」という選択肢があります。
なお、相続は株式譲渡には当てはまりません。株主が故人となった場合に、遺言に基づいて行われる手続きとなります。株主は相続することになる株式を含む財産を、後継者となる人と協議をしながら遺言書を作成して、来るべき日に備えます。
贈与とは、生前に行う財産譲渡方法です。贈与による株式譲渡は無償なので、株式を受け取る側の負担は少なく済みます。生前に譲渡できることから、双方の望むタイミングや、明確の決断の下に行うことができるのが特徴です。しかし、贈与は無償譲渡といえども贈与税という税金が発生することには注意が必要です。
未成年者は自分でお金を稼ぐ手段や財産に乏しいため、通常、未成年者へ株式を譲渡する場合は贈与という方法を採ることになります。贈与は、贈与する人とされる人の間で取り交わされる「諾成契約」と呼ばれる種類の契約です。
この諾成契約は口頭でも成立しますが、口頭であっても契約行為であることには変わりません。そして未成年者による契約行為には、親権者(法定代理人)の同意が必須となります。
親から子への贈与による株式譲渡は、親が一方的に得をして子どもが損をするという「利益相反行為」には当たらないため、親権者が承諾(同意)をすることで贈与は成立となります。
3-2 未成年者への株式譲渡(贈与)の手続き
贈与契約は口頭で成立するとしても、株式の所有者移転の一連の手続きは必要です。その手続きの概略を見ていきましょう。
最初に取り掛かるのは、株式譲渡の承認を行うための臨時株主総会の準備作業です。臨時株主総会は、取締役会による開催の決定を経て、株主の招集を行うことにより開催します。そして、臨時株主総会の場において株式譲渡の承認決議を行います。
なお、株主が1人だけの場合は臨時株主総会を開催しなくても良いのですが、この種の手続きは、書面(議事録)で残しておく方が確実です。すなわち、総会をしかるべき形式で開催しておくのが良いということです。
書面に残すのが良いのは、先に取り上げた贈与契約の契約書も同様です。先述の通り、贈与契約は親子間では口頭でも成立しますが、後日のトラブル回避や税務調査に備えて贈与契約書を残しておくのが確実です。
贈与契約書には贈与年月日や贈与する株式数を記載し、そして贈与者と被贈与者の名義で作成します。ここでは被贈与者は未成年者となるので、被贈与者の名前の下に親権者の欄も加えることで親権者の同意を得たことを示すようにします。
贈与手続きの最後は、非上場企業では株式の譲渡制限が通常かかっているため、贈与を行う前に株式発行会社に対して請求する名義の書き換えです。
名義の書き換えは、名義書換請求書に添付書類を添えて、贈与者と被贈与者が共同で行います。会社は、当該請求を元に株主名簿の名義を変更します。以上で贈与による株式譲渡の完了となります。
3-3 未成年者への株式譲渡(贈与)の注意点
最後に、贈与による株式譲渡の注意点を3つ見ていきましょう。注意点の1つ目は、先にも触れたように書面に残しておく、ということです。
特に贈与契約書は、贈与する株式の金額が110万円超となる場合には贈与税の申告義務が発生します。契約書の内容や贈与税について分からないことがある、また慎重を期す場合は、税理士や弁護士に相談をすると良いでしょう。
注意点の2つ目は、前項の贈与手続きをしっかりと踏む、ということです。手続きを順番通りに行い、不備がないようにしないと、譲渡が認められないことがあります。不安であれば、やはり税理士等の専門家に相談しながら行うのが良いでしょう。
注意点の3つ目は、家族間トラブルの種を極力なくすようにしておくことです。贈与者(親)が良かれと思う贈与であっても、被贈与者(子)が同じように思うとは限りません。
社会経験のない未成年者にはなおのこと、経緯や背景、注意点をしっかりと説明して、親子とはいえども双方納得の行く株式譲渡となるようにしましょう。
4 会社設立は未成年でも可能?会社を設立できない人とは?
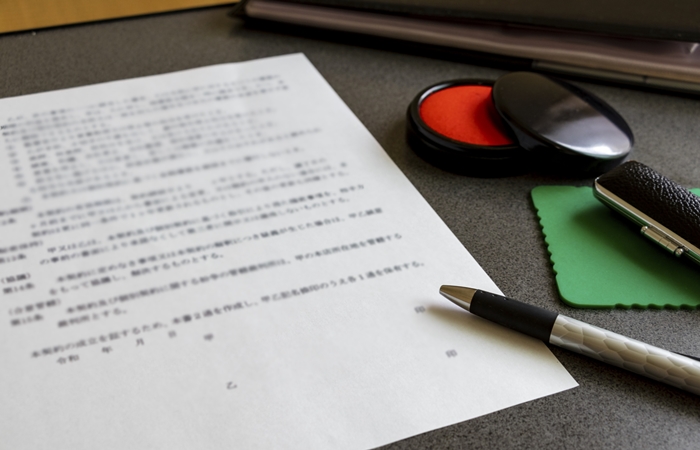
会社法においては、未成年でも会社を設立できると旨が規定されています。ただし、未成年の全てが会社を設立できる訳ではありません。印鑑登録をできる年齢が15歳なので、会社設立が可能な年齢は15歳となります。
会社を設立するには設立者の印鑑証明書が必要です。すなわち、印鑑登録をできない=会社を設立できないということになります。15歳未満は印鑑登録をできないため、会社設立もできません。また、会社法では、成年後見制度の対象となる被後見人は会社の取締役にはなれない、すなわち会社を設立できない、と規定しています。
他にも、会社法、破産法、そして金融商品取引法に違反をして罰則を受けた人は、以降2年間は会社の取締役にはなれません。そして上記以外の法律においても、禁錮刑以上の前科がつくことで取締役にはなれません。
なお、かつては債務超過などによる破産者も会社を設立できませんでした。しかし現在では、会社法が改正されて、破産者でも会社の取締役になることができるようになっています。
さて、未成年でも15歳以上という条件付きで会社を設立できるが、15歳未満は会社を設立できないということが分かりました。次に、15歳以上の未成年が会社を設立する際のハードル、また15歳未満は会社の設立に全く関係できないのかということについて見ていきましょう。
5 未成年が会社を設立するハードルと方法

15歳以上は会社を設立できる一方、15歳以上であっても社会においては未成年者であることに変わりはないため、未成年であることの制約を受けます。これは、15歳以上であっても独力では会社を設立できないことを意味します。
5-1 15歳以上の未成年が会社を設立する方法とハードルとは
未成年者は親権者の保護下にあり、契約締結等の法律行為を行う際には親権者の同意を得る必要があります。これは15歳以上か未満かに関わらず、全ての未成年が対象です。すなわち、未成年である以上、会社設立には親権者の同意や協力が不可欠です。
会社を設立するための条件の1つである印鑑証明書の取得においても、そして印鑑証明書に続く各種会社設立手続きにおいても、これらは法律行為となるため親権者の同意が必要です。
通常の(成人の)株式会社の会社設立手順の概略は、定款を作成して、定款認証を行い、資本金を払込し、登記申請書類の作成を行い、会社設立登記を行うというものです。これらは成人であっても手間のかかる煩雑な作業ですが、未成年者は更に親権者の同意や協力が必要となります。
例えば、上記の会社設立手順の概略の最初に挙げた「定款を作成」を例に見てみましょう。定款を作成した後は、その定款に会社設立者=「発起人」が署名押印をすることになっています。
発起人とは、会社設立が完了するまでの責任者とされる人のことです。発起人には年令制限はないため、未成年でも発起人になることができます。発起人は、設立する会社が株式会社である場合、定款作成後に「定款認証」を行います。
未成年の法律行為には親権者(法定代理人)の同意が必要でした。この定款認証は法律行為にあたるため、作成した定款の最後に、発起人すなわち未成年である自分の署名押印(印鑑登録した印鑑による)と、更に親権者の署名押印も必要になります。
そのため未成年者が定款認証を行う際には、添付書類として通常の発起人の印鑑登録証明書に加えて、親権者の実印押印済み同意書、親権者の印鑑登録証明書、戸籍謄本が必要になる、すなわち親権者の同意や協力が不可欠になるということです。
さて、発起人とは会社設立の完了の責を負う者ということでした。この責の1つに、会社の資金を供出するというものがあります。すなわち、発起人とは設立する会社の出資者であるということです。これは、もし設立する会社が株式会社の場合、発起人は必然的に株主となることを意味します。
株主とは、会社の所有者と同義ですが、必ずしも会社の経営者とイコールではありません。株式会社で経営に携わるものは「取締役」となり、株主と取締役の役割は区別されています。
ただし、株主と取締役は同一人物でも問題ないため、会社設立時の会社の多くは、会社設立者が取締役を兼任します。そして、会社法ではその取締役に対して年齢の制限を設けていないため、未成年者でも取締役になることができます。
また、印鑑証明書が必要な法律行為に該当するため、未成年者が取締役になるには親権者の同意が必要となります。
以上が15歳以上の未成年者が会社を設立する過程におけるハードルですが、未成年者の場合、上記以外にも会社設立には高いハードルがあります。そのハードルの1つが法人口座の開設です。
会社は営利目的団体であり、お金の入出金は必然的に起こるため、会社設立時には会社の預金口座が不可欠です。一般に、法人口座の開設は個人口座の開設よりも厳重に審査されます。
それに加えて、会社設立者がそもそも勤労経験のない(または少ない)未成年者となる場合、銀行によっては、会社設立者が未成年であるということを理由に法人口座の開設を不可としている可能性もあります。
また、設立後の会社を自宅以外とする場合、すなわち事務所を借りる場合や、あるいは事務所としての実体はない住所だけの貸借契約となるバーチャルオフィスの場合も、やはりそれらの賃貸借契約は法律行為に該当するため、親権者の同意や、親を代理人としての契約が必要となります。
このほか、会社の運営には資金が必要です。株式会社を設立するための費用だけでも約25万円が必要となり(電子定款としない場合)、それに加えて会社の事業運営のための資金を用意しなければいけません。
会社設立時の事業運営のための資金のことを「資本金」と呼びます。この資本金は会社設立時に用意しなければいけないものですが、1円でも構いません。ただし、少なければ少ないほど会社を設立してもできることは限られます。
未成年が独自に用意できる資金調達手段や金額は、ごく限られていると言って良いでしょう。素晴らしいアイデアがあったとしても、それを実現して世に広めるだけの商品開発力や広告宣伝費といった資金力がないと、絵に描いた餅となります。
会社を維持するためにも資金は必要不可欠です。会社の維持費には、自分の給料や電気代、事務用品費、パソコンやインターネット等の通信機器代等があります。事業を始めてから初めて気づく費用も多いはずです。維持費だけで資金が枯渇するようでは、事業の拡大は見込めずジリ貧になっていきます。
そのため会社設立時には、現実的にひと月あたりの事業運営費が幾らであるか見積もって、それに合わせて初期資金を準備することが重要です。資本金は、先に見たように1円でも良いのですが、目安としては少なくとも事業運営費の3ヶ月分以上、または100万円以上を用意したいところです。
5-2 15歳未満の未成年が会社を設立するのは不可能か
15歳未満は印鑑登録ができないため、会社設立者や取締役になることは不可能です。ただし、登記簿上では不可能となるものの、それは登記簿上の話しであって、15歳未満が会社内部で意思決定を行ったり、対外的に社長や会社設立者を名乗ったりすることは可能です。そのためには、まず親などの親権者に会社の設立と取締役等の役員に就任して貰うことが必要となります。
前項で見たような未成年者による法人口座の開設や資金調達、そして取引先との折衝というハードルにおいても、親権者すなわち登記簿上の設立者や取締役に表に出てもらうことで、道が拓ける可能性も高まります。
また、必ずしも会社を設立しなくても、事業主となれたり事業を行ったりできる方法があります。それは、個人事業主になるというものです。個人事業主となることに年齢の制限はなく、また会社設立のような手続きや費用も必要ありません。
そのため、実績を築くためにもまずは個人事業主から始める、というのが現実的で堅実な方法と言えるでしょう。事業が軌道に乗った際に改めて会社を設立する、いわゆる「法人成り」をすれば良いのです。
5-3 未成年者が資金を調達する方法
会社を設立できたとしても、未成年者には事業資金の調達という最も高いハードルが待ち構えています。一般に若ければ若いほど、お金の調達手段や財産額は少ないものです。
また未成年者の場合、資金調達のメジャーな手段である銀行からの融資も見込みも限りなくゼロであると考えたほうが良いでしょう。銀行の融資には同一企業、または同一業種に6年以上継続して勤務していること等が審査要件となっいるためです。
そのため、未成年者の現実的な資金調達先は第一に両親となります。両親の貯金から、あるいは自分の将来の学費として蓄えて貰っていた部分から、資金を捻出して貰うことが現実的な資金調達方法となります。
会社を経営していくためにはプレゼン能力が必要です。両親を最初のプレゼン先として、自分の起業アイデアや事業計画、さらには今後の勉強との兼ね合いや人生計画を説明して、協力を要請してみましょう。
資金調達方法には他にも、投資家に頼るという選択肢もあります。エンジェル投資家と呼ばれる投資家は、会社設立後間もない会社に対して資金を提供する個人投資家です。エンジェル投資家には様々なタイプがいますので、中には未成年であることの将来性や、事業の秘めている可能性を感じ取ることで、資金を提供する人もいるでしょう。
ただし、資金提供の条件が自社株式と引き換えである場合には注意が必要です。株式とは会社の持ち分ということですので、将来的に会社が大きくなった際に会社を乗っ取られる可能性があります。両親以外に資金を求める場合は、両親を初めとした周りの大人の意見を聞いて慎重に行うのが良いでしょう。
他には、クラウドファンディングという方法もあります。クラウドファンディングとは、商品やサービス内容、将来像をインターネットでプレゼンして、賛同を得た人から資金を募るという方法です。
資金提供者には、資金額に応じた商品やサービスをリターンします。クラウドファンディングは個人の(会社の)ホームページでもできますが、専用のサイトがありますので、そのサイトで行う方がより人目に触れる機会が高まります。
ただし、専用サイトの場合は手数料がかかり、また多くの人目に触れる反面、似たようなアイデアや先行商品がある場合はあっという間に埋もれてしまい、望んだ資金額を調達できないこともあります。
未成年は、若さによる将来性や瑞々しい感性をもってアピールすることができます。その利点を大いに活かして、会社を設立し運営するのが良いでしょう。






